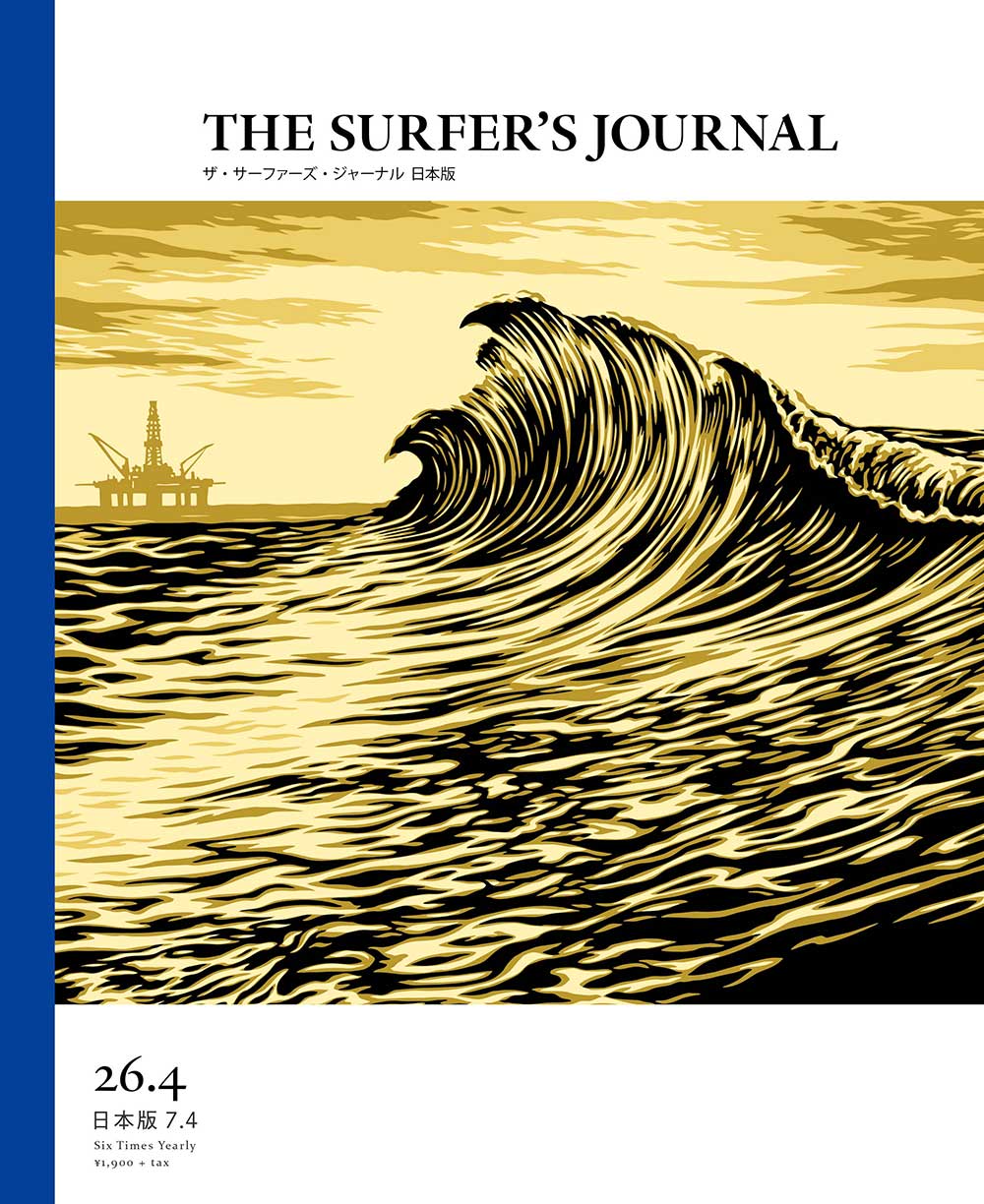
『THE SURFER’S JOURNAL』日本版は、米サーファーズ・ジャーナル社発行の隔月誌『THE SURFER’S JOURNAL』のフランス語に続く外国語バージョン。本物の“SURF CULTURE”を日本のサーフィン愛好家たちに向けて発信。『THE SURFER’S JOURNAL』同様、美しい印刷で紹介される素晴らしい写真は読者を虜にする。
そんなサーファーズ・ジャーナル日本版7.4号となる最新号が10月25日(金)発売になる。
まず最初のフィーチャーストーリーは、日本版のオリジナルコンテンツ、ロックホッパー・ウェットスーツを立ちあげた寺岡道廣と桜井喜夫、そして成尾均の3人の男たちの、サーフィンと海、下町の人情で結ばれた滑稽で奇想天外な物語である。

Three Amigos
「みっちゃんとイワトビペンギン夏ものがたり」
文:江本リク
生涯を通して人は、砂の数ほどの人々とすれちがい、会話を交わし、アリのように触覚を突き合わせて、互いにコミュニケーションをとりあっている。そうした無数にして無限大の人々との係わりのなかでも、強烈なバイブレーションに引かれ合い、触れ合うことで、共感を覚え、知人から友人へ、親友から仲間へ、そしてファミリーリレーションへと発展するケースも稀ではない。サーフィン、海、そして都会を舞台にした下町人情で結ばれた3人の男たちの、滑稽にしてハチャメチャで、アンダーグラウンドな昭和の夏物語がはじまろうとしている…
この号でもっともこころを揺さぶられたストーリーがチリの海岸線をガールフレンドと馬たちと旅をしながら、のんびりとサーフィンを楽しむひとりのサーファーの物語だ。
Pack and Saddle
「パック・アンド・サドル」
馬たちと旅したチリの海岸線。
文:マティ・ハノン
100ヘクタールもある新しい住処に馬たちがなじむのを見届けて、数日後にはぼくらが旅立つときがきた。「クーーダクダクダクダ!」ぼくのいつもの呼び声に、4頭の馬は頭を上げ、300ヤード先から一斉にこちらに向かって駆けてきた。ぼくは4本の人参を持っていて、それで少しだけ明るい気分になれた。サルバドールは別れを理解していたみたいで、鼻をぼくの肩に押し付けてきた。これまで100万回もしてきたように、ぼくは両手いっぱいのハグをした。彼の力強い大きな心臓の音が耳の奥に響いた。
「寂しくなるよ」胸がいっぱいだった。ぼくはこれで馬を持たないホースマンになったのだ。そのおなじ日、ヘザーからカナダに帰国することを伝えられた。彼女は最近、前ほど笑っていなかった。山を越えながら、何度か喧嘩もした。
「わかってね」とヘザーは言った。「うん、それがきみの望むことなら」とぼくは答えた。
極寒のパタゴニアに、彼女なしで行くことになるのだ。ふと、あの崖から落ちる滝の近くで割れていた波のことを思いだした。
どんなときも楽観主義であるヘザーが言った。「マティ、馬たちはすごく嬉しそうね。この場所、本当にすばらしいもの。美しい谷には美味しい草がたくさんあって、豪快な川が流れていて、立派な火山が見守っていて。こんなすてきな森もあるし」
「うん、すごくきれいだね」景色を見ようとヘザーに背中を向けながら、そっとそう答えた。でも、それは嘘だった。目の前の視界がぼやけて、ぼくにはなにも見えなかったのだから。
もうひとつ、今号で心を打たれたストーリーがある。相変わらず戦争に明け暮れるアフリカ大陸、そこで活躍する戦争カメラマンがいる。ニック・ボスマ、彼はまたサーフィンを撮るサーフ・フォトグラファーでもある。

War and Waves
「戦争と波」
洞窟の奥へと匍匐前進する、戦場フォトジャーナリスト、ニック・ボスマ。
文:ウィル・ベンディックス
写真:ニック・ボスマ
アフリカ大陸で20年以上の経験をもつベテラン戦場カメラマンのボスマは、2003年に終結した悲惨なリベリア内戦の爪痕をフィルムに収める任務を請け負っていた。行動をともにした司令官アイジャモンは軍首脳という触れ込みだったが、精神の錯乱した愚か者といえなくもない。当時リベリアを覆っていた狂気のさなか、それを見分けるのは容易ではなかった。
首都モンロビア郊外では、政府転覆をもくろむ武装勢力と指揮官チャールズ・テイラー率いる軍隊との衝突が絶えず、ボスマはそんななか戦闘現場に出向いた。護衛についてくれたのは司令官たったひとり。悪名高いテイラー軍の兵士らは、誘拐した子供の一団にAK-47を持たせ、ヤシ酒と“ブラウン・ブラウン”(コカインと火薬を混ぜ合わせたもの)を与えて戦場に送り込んだ。
テイラー軍のなかには、略奪したかつらやウェディングドレスを身につける兵士もいた。それが弾除けになると信じていたからだ。敵対する反政府軍にも女装や民間人の装いで戦う兵士が後を絶たず、敵味方を区別するのは実質的に不可能だった。

The Caretaker of Intangible Ingredients
「世話役」
生粋のサンディエガン、ハリー・スキップ・フライのパーソナル・クイバー。
文:クリス・アーレン
「サーフボードがいいんじゃなくて、ライダーが上手なんだよ」。それはサーフィンの世界に長年語り継がれた常套句。しかしスキップ・フライの場合、それは例外で、ライダーとボードを切り離して語ることはできない。これまでに開発されたフライのクイバーについて語りながら、ライダーでもあるその男について語ってみよう。

The Big Boogie
「ビッグ・ブギー」
“害虫”やら“クズ”などと揶揄されながらも、そんなのどこ吹く風。ボディーボーダーたちは今も進化しつづけ、バレルをチャージしつづける。
文:キンボール・テイラー
「1980年代、おれたちはボディーボーダーなんてまったく認めていなかった」。そう答えるのは歴史家で元『サーファー』誌編集者のマット・ワーショー。「私たちは、神が創られたこの青い地球上でもっとも洗練されたウェーブライダー、マイク・スチュワート(ボディーボード世界チャンピオン9回、パイプライン・チャンピオン15回、ボディーサーフィン・チャンピオン14回)ですら容赦しなかった。ボロクソに叩いたものだ」





